近年、世界経済の不確実性が高まる中で、特に米国の景気後退(リセッション)の可能性が注目されています。中でも、関税強化がもたらす経済への影響と、過去のリセッション予測指標として知られるイールドカーブの動向は、多くの専門家が注視している要素です。本記事では、主要金融機関が上方修正した「リセッション確率45%」という見通しがどのような背景から生まれたのか、そしてイールドカーブの現状と合わせてどのように解釈すべきかについて、その詳細と経済への深い洞察を加えて詳しく解説いたします。
関税強化がもたらすリセッション確率45%の背景と主要機関の見解
米国のトランプ政権による対中・対欧米の相互関税措置の発動を控え、複数の大手金融機関が景気後退発生確率を大幅に引き上げました。これは、単に貿易摩擦が激化するというだけでなく、金融市場のセンチメント悪化が急速に進むという懸念を迅速に反映した動きと言えます。
例えば、シティグループは、関税が米経済に「スタグフレーション的ショック」を与える可能性を指摘し、年後半への景気後退リスク上昇を警告しました。ここで言うスタグフレーションとは、経済成長が停滞する中で物価が上昇する状態を指します。
関税は輸入コストを押し上げ、それが最終的に消費財の価格に転嫁されることでインフレを加速させます。同時に、貿易量の減少やサプライチェーンの混乱が企業の生産活動や投資意欲を減退させ、経済成長を鈍化させるというメカニズムが働くと考えられます。この複合的な悪影響が、リセッション確率を40~45%に修正する根拠となりました。
また、ゴールドマン・サックスは4月初旬の追加関税発動前後に短期間で2度、12カ月以内のリセッション確率を35%から45%へと引き上げています。これは、関税による不確実性が企業投資を抑制し、サプライチェーンの再構築にかかるコスト増が企業収益を圧迫するとの見方が強まったためです。ロイターのエコノミスト調査でも、前年同月の25%から45%へと急上昇するなど、広範な見通しの上方修正が見られました。
これらの見通しは、主に貿易戦争による企業の設備投資抑制、消費者・企業心理の著しい悪化、そして金融条件のタイト化(利回りスプレッド拡大)を根拠としております。特に、不確実性の高まりは、銀行の貸し出し姿勢を慎重にさせ、企業が資金調達しにくくなることで、さらなる投資の落ち込みを招く可能性があります。
イールドカーブ逆転とは何か その歴史的予測精度
イールドカーブとは、債券の残存期間と利回りの関係を示した曲線のことです。通常、期間が長い債券ほど利回りが高くなる「順イールド」の状態ですが、短期金利が長期金利を上回る「逆イールド」は、過去数十年でリセッションを高い精度で予測してきた指標として知られています。
この現象がなぜ景気後退の強力な先行指標となるかというと、それは債券市場の参加者の将来の経済見通しを反映しているからです。通常、投資家は長期的に資金を貸し出すリスクに対して、より高いリターン(利回り)を求めます。しかし、将来的に景気が悪化し、中央銀行が利下げに踏み切ると予想される場合、長期金利は現在の短期金利よりも低くなることがあります。これは、市場が将来の経済活動の鈍化とインフレ率の低下を見込んでいることを示唆しています。
特に「2-10年国債利回りスプレッド」の逆転は注目されており、過去のデータでは、このスプレッドが逆転した後、平均18週から3年という「ラグ(時間差)」を経てリセッションが発生する傾向が見られました。このラグは、金融政策の波及効果や企業・家計の行動変容に時間を要するためと考えられています。
1955年以降、2-10年スプレッドの逆転シグナルは28回発生し、そのうち22回でその後にリセッションが到来しているという実績があります。例えば、2000年のITバブル崩壊前や、2008年のリーマンショック前にも、このイールドカーブの逆転が明確なシグナルを発していました。この高い予測精度から、イールドカーブの動向は経済の先行指標として非常に重視されています。
現在のイールドカーブ状況と景気後退シグナル
2025年7月3日時点の米国債利回りを見ると、2年物国債が3.88%、10年物国債が4.35%となっており、スプレッド(10-2年)はプラス0.47%です。これは、2025年初頭に見られた逆転が解消され、現在は順イールドに戻っていることを意味します。この変化は、市場が一時的に中央銀行の利上げサイクルが終了し、あるいは将来的な利下げの可能性を織り込み始めたことで、短期金利の上昇が一段落し、長期見通しへの警戒が若干後退した局面にあると解釈できます。
しかしながら、イールドカーブの傾きは過去平均と比べると依然として「フラット化」しており、これは潜在的な景気後退リスクを依然として孕んでいる状態であると解釈できます。フラットなイールドカーブは、短期金利と長期金利の差が小さい状態を指し、これは市場が将来の経済成長やインフレに対して強い自信を持っていないことを示唆します。
完全に正常な順イールドに戻ったわけではないため、この平坦化は、経済が持続的な成長軌道に乗るにはまだ課題が多いことを示唆しており、引き続き注意が必要です。もし経済状況が再び悪化すれば、このフラットなカーブは容易に逆転へと転じ、新たな景気後退シグナルを発する可能性も秘めています。
関税リスクとイールドカーブ指標の統合的解釈と今後の展望
直近のリセッション確率45%という見通しは、金融市場のセンチメント悪化を迅速に反映したものであり、その信頼性は高いと言えます。これは、関税という直接的な経済ショックが、企業や投資家の心理に与える影響を強く捉えたものです。しかし、これは調査ベースの予測であり、実際の景気後退発生までには時間差があることを考慮する必要があります。調査は瞬時の市場心理を捉える一方で、実際の経済活動への影響が顕在化するにはタイムラグが生じます。
一方、イールドカーブの逆転は、2022年7月の逆転が2020年のコロナ禍後と同様に警戒シグナルを発していたように、歴史的に確度の高い予兆とされてきました。イールドカーブは、市場の期待と流動性条件を反映する、より構造的な指標と言えます。2025年に順イールドに戻ったとはいえ、その傾きの平坦化は依然としてリスク要因です。
これら二つの要素を総合的に判断すると、関税措置による直接的な「ショック」と、イールドカーブの歴史的シグナルを併せて考慮した場合、2025年後半以降の景気後退リスクは依然として高いと見られます。しかし、確率45%はあくまで「12カ月以内の大まかな見通し」であり、実際のリセッション発生の可否は、FRBの追加利下げ、財政政策対応、そしてグローバルな需要動向など、他の複数のマクロ指標にも左右されるため、継続的なモニタリングが不可欠です。
具体的には、製造業PMI(購買担当者景気指数)、小売売上高、雇用統計、企業収益、グローバル貿易量などの指標を注視することで、より包括的な経済状況の把握が可能となります。中央銀行の利上げ・利下げのタイミングや、政府の財政出動の規模と効果も、景気動向を大きく左右する要因となるでしょう。
結論
関税強化によって「リセッション確率45%」という警告が発せられたことは、根拠のある見通しであると言えます。これは、貿易摩擦が経済心理と実体経済に与える影響を強く反映したものです。しかし、イールドカーブが現在順イールドに正常化しているという現状を踏まえると、単一の指標に依存せず、来年以降の経済動向を多角的に見極める必要があります。
金融市場のセンチメント、企業活動、消費者心理、そして中央銀行の政策など、様々なマクロ経済指標を総合的に分析し、慎重な判断を下していくことが求められます。複雑な経済環境の中で、柔軟かつ適応性の高い戦略が、今後の経済動向を乗り切る鍵となるでしょう。
こちらもおすすめです
FRBは関税インフレを無視できるか ?最新の金融政策動向
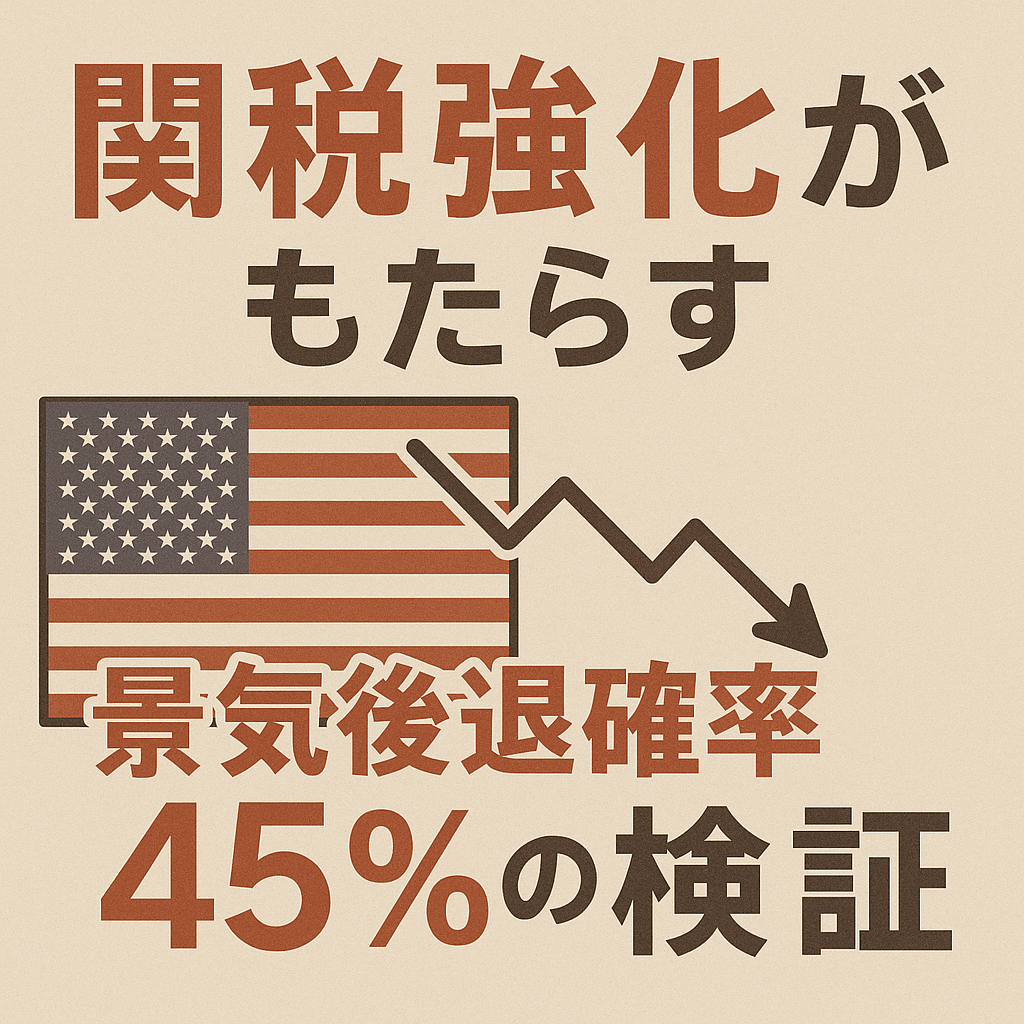
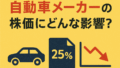
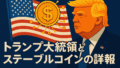
コメント