2025年5月に発表された米国CPIでは、表面上はインフレ鈍化が進む一方で、関税と粘着インフレという二つの構造的要因が注目されています。本記事では、最新CPIの動向をより深掘りし、今後の金融政策や家計への影響をわかりやすく整理します。
最新CPI発表でわかった物価の実態
5月の米CPIは予想を下回る+0.1%の上昇にとどまり、前年同月比では+2.4%の上昇率となりました。ガソリン価格の低下が全体を押し下げた一方、住居費や食品の価格は引き続き上昇しています。特に家賃の上昇は依然として物価全体を高める要因であり、多くの家庭の生活費に影響を与えています。
大型家電などに影響する関税の実態
鉄鋼・アルミ関税や対中関税の維持・強化により、大型家電や玩具など特定の商品の値段が大幅に上がっています。企業は在庫調整を進めながらもコスト転嫁を避けきれなくなり、一部では小売価格を段階的に引き上げています。この動きが今後さらに広がる可能性が指摘されています。
粘着インフレとは何か、その正体を探る
FOMCの議事要旨では、インフレが一時的に下がっても住宅費やサービス価格、賃金といった要素が根強く残り、物価の高止まりを引き起こす「粘着インフレ」が強調されています。特に賃金上昇率が依然高水準にあり、非住宅サービスの価格が下がりにくい点が大きな懸念材料です。
労働市場と供給制約の影響
労働市場の逼迫や移民制限などが特定業界で人手不足を招き、企業は人材確保のために賃金を引き上げざるを得ません。その結果、サービス業の価格は高止まりし、家計負担が増しています。医療や教育といった分野では市場のメカニズムだけでは価格抑制が難しく、これがインフレの粘着性を高めています。
関税がもたらす追加リスク
関税は企業のコスト構造を変えるだけでなく、報復関税の可能性やサプライチェーンの見直しを促し、長期的に価格を押し上げる恐れがあります。最近では大手小売業が追加の値上げを発表しており、企業と消費者の双方に重くのしかかるコストとなっています。
金融政策に及ぶ粘着インフレの影響
FOMCは当面の間、高金利政策を維持する見通しです。関税や粘着インフレが残る以上、早期の利下げは難しく、インフレが目標値に戻るまでには時間がかかるとみられています。市場は利下げを織り込む動きも見せていますが、FRBは慎重姿勢を崩していません。
家計が注視すべき今後のポイント
物価の下方硬直性は家計にとって大きな負担です。住宅費やサービス費用の見直し、消費行動の工夫が重要になります。また、関税の影響を受けやすい商品については、価格動向を注視することが求められます。
まとめ
最新CPIの結果からは、単なるエネルギー価格の変動だけでは説明できない関税と粘着インフレの影響が浮き彫りになりました。金融政策の行方も含め、今後の米国経済はこれらの要素に大きく左右されます。最新動向をしっかりと把握し、賢い資産管理を心がけましょう。
これも、おすすめです。
FRBは関税インフレを無視できるか ?最新の金融政策動向


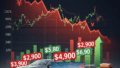
コメント