「責任ある積極財政」の基本的な考え方と目的
最近、政治・経済ニュースで「責任ある積極財政」という言葉をよく耳にされると思います。これは、単に政府がお金を使う「積極財政」だけを意味するものではありません。
この政策の基本的な考え方は、「景気悪化や構造的な課題(少子高齢化、安全保障リスクなど)に対し、政府がタイミングよく十分な財政支出を積極的に行う一方で、将来の財政の持続可能性や市場の信認も同時に考慮する」というものです。
つまり、現在の支出を将来の税収増加につながる成長投資として位置づけ、「決して無責任なバラマキではない」という責任感を伴わせている点が特徴です。例えば、成長が安定的に達成できれば、経済状況に合わせて将来的に財政政策を縮小・均衡させていくという出口戦略も視野に入れています。
なぜ今、この政策が求められているのか
この考え方が今、特に日本で注目されている背景には、長期にわたるデフレと低成長があります。
長期間、所得が上がらず、若年層が将来に希望を持てない状況が続きました。また、新型コロナウイルスのパンデミックや国際情勢の不安定化により、「経済安全保障」や「サプライチェーンの強靭化」といった、国が戦略的に先手を打って投資すべき分野が明確になったことも大きな要因です。
従来の「歳出抑制・財政健全化重視」一辺倒の政策から、構造的な課題に対し支出を通じた未来投資へシフトし、停滞した経済を根本から底上げしようとする機運が高まっています。具体的には、物価高騰に苦しむ国民生活への直接支援や、AI、半導体、防衛といった中長期的に重要な分野への戦略的投資が想定されています。
10年後(2035年)に想定されるポジティブシナリオ
この「責任ある積極財政」の政策が計画通りに機能し、一定の成果を上げた場合、約10年後の2035年頃には以下のような経済・生活環境が想定されます。
|
項目 |
影響 |
|---|---|
|
経済・物価 |
政府による成長分野への投資が民間を刺激し、名目成長率が2〜3%程度を安定して維持します。物価は年1.5〜2%の上昇となり、デフレからの完全な脱却が定着します。 |
|
年金制度 |
賃金と保険料収入の改善により、年金財政が安定します。年金支給額の実質的な減少を調整する「マクロ経済スライド」の抑制効果が発動し、年金の実質減額スピードが緩やかになることが期待されます。 |
|
税制・社会保障 |
経済成長に伴う税収増により、財政再建の圧力は残るものの、消費税などの大型増税の議論は一時的に遠のく可能性があります。 |
|
資産運用 |
日本の株式市場は、政府の成長戦略に沿った分野(AI、脱炭素、防衛など)を中心に底堅い成長が見込めます。NISAやiDeCoといった制度を活用する個人にとって、資産が増えやすい好環境となります。 |
20年後(2045年)に備えるべき財政重圧シナリオ
一方で、積極財政の「責任ある」部分、すなわち「成長につながる」という前提が崩れ、財政規律の回復が遅れた場合、20年後の2045年頃には財政重圧によるリスクが顕在化する可能性があります。
|
項目 |
影響 |
|---|---|
|
経済・財政 |
高齢化と少子化が一段と進行し、社会保障支出が急増します。財政再建の道筋が見えず、国債残高の拡大に市場が不安を感じ、長期金利が2〜3%台に上昇するリスクがあります。 |
|
年金制度 |
財政の制約が厳しくなり、年金水準は実質的に現在よりも2割前後低下し、受給開始年齢が68歳前後へ引き上げられる可能性が高まります。物価上昇に年金が追いつかず、高齢者の生活コスト上昇リスクが現実化します。 |
|
税・社会保険料 |
財政再建のため、消費税率が20%前後まで引き上げられる議論が現実味を帯びます。医療・介護の自己負担割合も引き上げられ、高齢者の可処分所得が大きく減少します。 |
|
資産運用 |
日本経済の信認低下から円安基調(例:1ドル=180円〜200円)が続く可能性があります。外貨建て資産を持つ方は円安による恩恵を受け、国内金利上昇により国内債券の利回りも上昇します。 |
FP視点での結論と準備すべき資産運用戦略
この「責任ある積極財政」という政策は、日本経済の大きな方向性を示す「マクロ地図」として捉えることが重要です。お客様へのアドバイスの軸として、以下の実践的なステップをご提案します。
-
長期成長テーマ×インフレ対応型の資産配分を基本に 2035年の成功シナリオを見据え、政府が戦略的投資を行うAI、インフラ、防衛などの分野に連動する株式やETF(上場投資信託)、および不動産(REIT含む)など、インフレに強い資産への分散投資を強化します。
-
国内外の通貨分散を極めて重要視する 2045年の財政重圧シナリオに備え、円資産に偏りすぎない設計が必須です。外貨建ての株式、債券、グローバルETF、外貨建て年金保険などを活用し、円の信認低下リスクに備えた通貨分散を図ります。
-
年金・税制の将来を見据えた「二段構え」設計の徹底 公的年金に加えて、iDeCoやNISAなどの優遇制度を最大限活用した自助努力型の資産形成を「第二の年金」として確立します。特にシニア層の顧客には、将来的な医療費・介護費の自己負担増加に備えるための現金流動性(生活防衛資金)の確保も重要なアドバイスとなります。
政府の積極的な動きは大きなチャンスをもたらしますが、同時に不確実性も伴います。これらのシナリオを総合的に判断し、リスクを管理しながら積極的な資産運用を行うことが、将来の安心につながる鍵となります。
こちらもおすすめです。


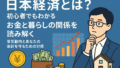
コメント