今回は、アメリカにおける税金と支出の仕組みについて考えていきたいと思います。
アメリカの経済ニュースを見ていると、「財政赤字」や「連邦債務」といった言葉が頻繁に登場します。これらはすべて、国の財政(税金と支出)の仕組みと密接に関わっています。
本記事では、アメリカの連邦政府が、どのように私たちや企業から税金を集め(歳入)、それを何に使い(歳出)、そして赤字が発生したときにどう対応しているのかを、初心者の方にも理解できるよう、段階を追って分かりやすく解説していきます。
1. アメリカの財政政策 全体像と「収入→支出→借金」のサイクル
連邦政府の経済政策、特に「財政政策」の核となるのは、**税金を集める(歳入)**ことと、**集めたお金をどう使うか(歳出)**を決めることです。この二つを通じて、景気の調整や社会的な役割を担っています。
そして、歳入よりも歳出が上回った場合、その不足分は「国債」を発行して市場から借り入れます。これが政府の「収入 → 支出 → 借金」という基本的なサイクルです。
このサイクルを、超簡略化したフローチャートで見てみましょう。
【図解イメージ:連邦財政の簡易フロー】
国民・企業が税金を支払う
↓
連邦政府(歳入)
↓
使い道を決める
↓
┌────────────┬─────────────┐
│ 義務的支出 │ 裁量的支出 │
│(例:年金、医療) │(例:国防、教育) │
└────────────┴─────────────┘
↓
収支差(黒字/赤字)
↓
赤字なら国債を発行し借金
国の財政は、毎年自動で決まる支出と、議会が毎年議論して決める支出のバランスで成り立っているのがポイントです。
2. 連邦政府の「歳入」構造 主な税金の種類と比率
では、連邦政府のお金は具体的にどこから来ているのでしょうか。歳入の大部分を占めるのは、以下の3つの大きな柱です。
歳入の3本柱(構成比は年により変動します)
-
個人所得税(Individual income tax)
-
特徴: 歳入の中で最大の柱です。給与、事業所得、投資収益などに課税されます。所得が高いほど税率が高くなる「累進課税」が採用されています。
-
比率: 近年は連邦歳入の約半分弱を占めることが多いです。
-
-
社会保険税(Payroll taxes)
-
特徴: 社会保障(年金)や医療保険(メディケア)の財源となる税金で、給与から天引きされます(雇用主と従業員が折半で負担)。
-
比率: 全体の約25%から35%程度を占めることが多いです。
-
-
法人税(Corporate income tax)
-
特徴: 企業の利益にかかる税金です。
-
比率: 個人所得税や社会保険税に比べると比率は小さく、近年は10%前後、あるいはそれ以下になることもあります。
-
【図解イメージ:連邦歳入の主な構成比(概念図)】
■■■■■■■■■■ 個人所得税(約50%)
■■■■■■ 社会保険税(約35%)
■■ 法人税(約10%)
□ その他(物品税、関税など)
このデータから分かるように、アメリカの連邦財政は個人からの税収(所得税と社会保険税)に大きく依存していることがわかります。
3. 「歳出」の分類 義務的支出と裁量的支出、利払いとは
連邦支出は、大きく分けて3つの主要な区分に分類されます。
A. Mandatory(義務的支出)
法律によって支出が義務付けられている項目です。受給資格さえ満たせば、毎年議会の承認を待たずに自動的に支払われます。
-
主な中身: 社会保障(Social Security/年金)、メディケア(高齢者向け医療保険)、メディケイド(低所得者医療)などが該当します。
-
傾向: 高齢化や医療費の上昇に伴い、この項目は年々増える傾向にあり、長期的な財政課題となっています。
B. Discretionary(裁量的支出)
毎年、議会で予算を審議し、その年の歳出法として決定される支出です。
-
主な中身: 国防費がこの枠の中で最も大きな比率を占めます。その他、教育、運輸インフラ、研究開発、司法、行政費用などがここに含まれます。
-
傾向: 毎年の政策や政治的な争点によって配分が大きく変わります。
C. Interest(利払い)
過去の財政赤字を補うために発行した国債に対する利子(利息)の支払いです。
-
傾向: 債務残高や市場の金利水準によって変動し、利払いが増えると、教育やインフラなどの裁量的支出を圧迫することになります。
【図解イメージ:連邦歳出の内訳(簡易円グラフイメージ)】
支出合計(100%)
├─ ■■■■■■■■■■■■ 義務的支出(Mandatory:約50-60%)
├─ ■■■■■■■■■ 裁量的支出(Discretionary:約25-35%)
└─ ■■■ 利払い(Interest:約5-15%)
4. 予算は誰がどう決めるのか? 議会と大統領の役割
連邦予算の策定プロセスは非常に複雑ですが、要点をまとめると以下のようになります。
【図解イメージ:予算決定の流れ(簡易)】
1. 大統領(OMB)が予算案を作成・提出
↓
2. 議会(上下両院)が予算の総枠(予算決議)を審議
↓
3. 各委員会の専門部会で裁量的支出の配分を決定(歳出法案)
↓
4. 大統領が法案に署名して法律として成立
↓
5. 財務省(Treasury)が支出を実行(不足があれば国債を発行)
このプロセスの中で、議会が大統領案に合意できず、期日までに予算が成立しないと、**政府機関の一部が閉鎖(シャットダウン)**したり、「暫定予算」でつなぐといった実務上の問題が発生することがあります。
5. 財政赤字と国債がアメリカ経済に与える影響
連邦政府のその年度の歳入(税金)が歳出(支出)よりも少なかった場合、それは財政赤字となります。この赤字を補うために市場から借り入れたお金の合計が**公的債務(国の借金)**です。
赤字・債務の影響
-
利払いによる予算圧迫
-
債務が増えると利払いも増え、将来の裁量的支出(教育やインフラなど)に使える予算が減ってしまいます。
-
-
短期的な景気刺激
-
景気が悪いときに政府が支出を増やして赤字になっても、需要を創出して経済を回復させる効果があります。そのため、「赤字=常に悪」というわけではありません。
-
-
長期的な影響
-
債務が過度に増大すると、市場の金利が上昇したり、将来の経済成長を妨げたりする可能性があります。
-
政府は景気や社会情勢に応じて、税制の変更(減税や増税)や支出の増減を行い、経済を安定させるための「政策のてこ」として財政政策を活用しています。
まとめ
アメリカの連邦財政は、私たちの生活を支える重要な仕組みです。
-
歳入の柱: 歳入は、個人所得税と社会保険税の二つが大部分を占めています。
-
歳出の柱: 歳出は、法律で決まった義務的支出(年金・医療)が大きな割合を占め、これが財政の長期的な課題となっています。
-
赤字と債務: 歳入と歳出の差が赤字となり、国債発行で賄われます。その増減は経済状況や政策によって大きく変動します。
この仕組みを理解すると、アメリカの政治・経済ニュースや政策論争がより深く理解できるようになるはずです。
こちらもおすすめです。
初心者向け|アメリカの経済・金融をニュースより分かりやすく学ぶ方法
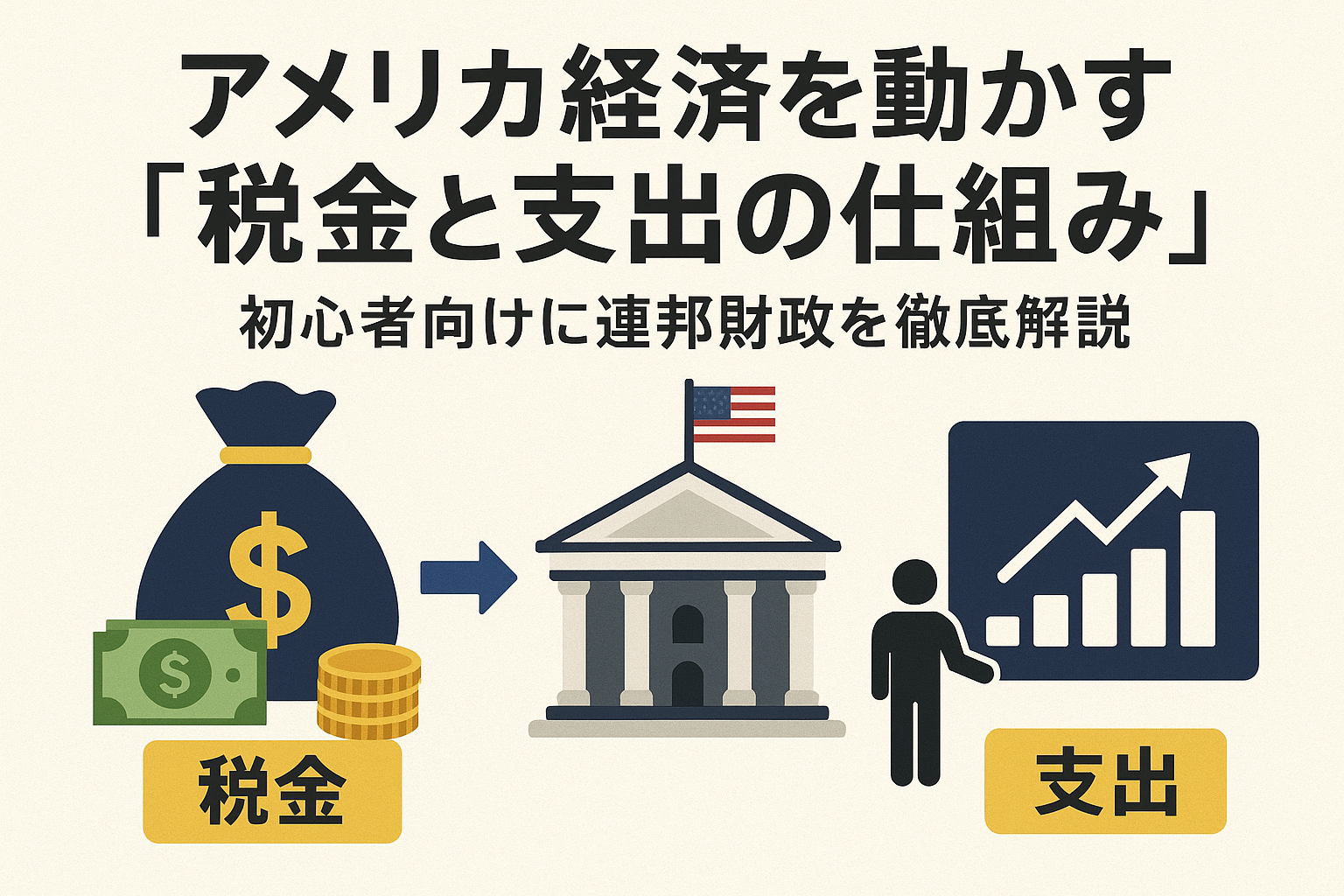
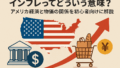

コメント