トランプ政権による関税発表のような市場を揺るがす出来事があった際、投資家はポートフォリオを守るための有効な手段を常に模索しています。特に「高配当株は関税ショックの避難先になるか」という疑問は、多くの投資家が抱く関心事ではないでしょうか。本記事では、過去のデータに基づき、高配当株、特に連続増配株が市場の混乱期にどのような役割を果たしたのかを詳しく解説し、今後の投資戦略への示唆をお伝えします。
関税ショック下での高配当株の驚くべきパフォーマンス
2025年3月26日から5月9日という、トランプ政権による相互関税発表後の期間において、配当利回り重視の「連続増配株」は、日本株平均を大きく上回るパフォーマンスを示しました。この期間、日経平均株価が-1.4%、TOPIXが-2.8%と下落する中、連続増配株指数は+3.3%と堅調に推移しました。また、東証リート指数も+0.7%とプラスを維持しており、市場全体が下落する中で、特定の資産クラスが有効な避難先となったことが明確に示されています。これは、関税ショックという不確実性の高い状況下で、連続増配株が投資家の資産を守る役割を果たしたことを意味しています。
なぜ高配当株が「避難先」となり得たのか
高配当株が市場の混乱期に強さを見せるのには、いくつかの理由があります。その一つが「インカムゲインの安定感」です。配当という確定的なキャッシュフローは、株価が下落する局面においても投資家にとっての安心材料となります。これにより、株価下落時の売り圧力が和らげられ、株価の底堅さが保たれる傾向にあります。市場が不安定な時ほど、確実なリターンが得られる配当の価値が再認識されるのです。
内需・ディフェンシブ特性がもたらす強み
高配当株の中でも、特に内需系や連続増配銘柄は、その「内需・ディフェンシブ色の強さ」が特徴です。これらの企業は輸出依存度が低く、関税リスクのような外部環境の変化による影響を受けにくい傾向があります。経済全体が不透明な状況下では、景気変動に左右されにくい安定した事業基盤を持つ企業が選好されるため、内需主導型の高配当株は、投資家にとって魅力的な選択肢となるのです。
割安感と資金シフトの加速
市場が混乱し、全体的に株価が下落する局面では、多くの銘柄が割安な水準に放置されることがあります。このような時、高配当株は「相対的なバリュエーション」の観点から注目を集めます。単純に配当利回りの上昇を狙った買い戻しが活発化し、PBR1倍割れなど、本来の企業価値よりも割安と判断される銘柄への資金シフトが加速する傾向が見られます。これは、市場の混乱が、優良な高配当銘柄を「バーゲンセール」状態にする可能性があることを示唆しています。
今後の投資戦略への示唆と注意点
連続増配株や高配当内需銘柄は、関税ショックや地政学リスクによる急落時に「バーゲンセール」化する可能性が高く、有効なディフェンシブ選択肢となります。市場全体が下落する中で、これらの銘柄は相対的な価値を保ち、投資家のポートフォリオを下支えする役割を果たすことが期待されます。
ただし、投資戦略においては注意点もあります。関税懸念の解消後には、これまで売られていた外需・グロース株の反発も見込まれるため、高配当株に過度に集中することは避けるべきです。市場のサイクルや経済状況の変化に対応するためには、タイミング分散(積立投資)と銘柄分散を併用し、リスクを適切に管理することが重要です。これにより、どのような市場環境においても、安定した投資成果を目指すことが可能となります。
こちらもおすすめです
【最新CPIは関税粘着インフレの正体】米物価に潜む本当のリスクを徹底解説

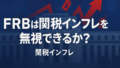

コメント